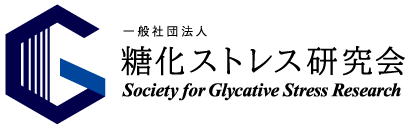2025/04/24
食品中機能性成分の効用を見直す! 食品中の善玉AGEsの効用
第30回糖化ストレス研究会が2025年5月23日(金)東京ビッグサイトのifia JAPAN 2025/HFE JAPAN 2025 にて開催されます。
ifia JAPAN 2025(第30回国際食品素材/添加物展・会議) / HFE JAPAN 2025(第23回ヘルスフードエキスポ)
日時:2024年5月23日(金)10:20~16:40
会場:東京ビッグサイト(南棟/会議ホール)
会長:米井嘉一(同志社大学)
共催:ifia Japan 2025 (食品化学新聞社)
5月23日(金)会場 608
K 第30回 糖化ストレス研究会 ~食品中機能性成分の効用を見直す! 食品中の善玉AGEsの効用~
プログラム
| 10:00 ~ | 受付 | |
| 10:15 ~10:20 | 理事長開会挨拶 | |
| 10:20 ~ 11:00 | 一般講演① | 食品中AGEsの測定とその課題 ~誤解をひもとく~ 同志社大学 八木雅之 |
| 11:10 ~ 11:50 | 一般講演② | 機能性食品因子による生体の酸化ストレス応答 同志社大学 市川 寛 |
| 11:50 ~ 13:00 | 休憩 | |
| 13:00 ~ 13:30 | 一般講演③ | コーヒーの健康効果 全日本コーヒー協会 岩井和也 |
| 13:40 ~ 14:20 | 一般講演④ | 食品中の抗糖化成分 株式会社SL Creations 健康サポート推進室 秋山里実 |
| 14:30 ~ 15:00 | 一般講演⑤ | メイラード反応をどのような形で食品に応用しているか 昭和化学工業 研究室 波多真一郎 |
| 15:10 ~ 15:50 | 一般講演⑥ | 食品中AGEsは悪くない:おいしいものは人を幸せにする 同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンター / 糖化ストレス研究センター 米井 嘉一 |
| 16:00 ~ | 会長閉会挨拶 |
全日本コーヒー協会
岩井和也
はじめに
コーヒーの豊かな風味は、生豆を焙煎する過程で生じるメイラード反応、糖のカラメル化、クロロゲン酸と糖の熱反応など、さまざまな化学反応によって生み出される。これらの反応により、900種類以上ともいわれる香気成分に加え、コーヒー特有の褐色色素も生成されるため、コーヒーはAGEs(終末糖化産物)を含む代表的な飲料といえる。過剰なAGEsの摂取や蓄積が健康に及ぼす影響については議論がある一方、コーヒーがもたらす健康へのポジティブな効果は、近年、多くの研究によって明らかにされている。代表的な研究として、国立がん研究センターによる多目的コホート研究では、コーヒーをほとんど飲まない人と比較して、1日3〜4杯飲む人の全死亡リスクが24%低下し、ハザード比は0.76(95%信頼区間:0.70〜0.83)であると報告された。また、2017年にはコーヒーに関する初のアンブレラレビューが発表され、67の健康アウトカムとの関連が調査され、特に肝疾患、パーキンソン病、アルツハイマー病、2型糖尿病などに対する有益な効果が示された。
クロロゲン酸類
コーヒーに含まれる代表的な健康成分のひとつに、ポリフェノールの一種である「クロロゲン酸類」がある。コーヒーは300種類以上のクロロゲン酸類を含み、抗酸化作用、抗炎症作用、脂質代謝促進作用などが確認されている。岐阜県高山市在住の29,079人を16年間追跡調査した「高山スタディ」では、ポリフェノール摂取量が多いグループの死亡リスクが有意に低いことが示され、その主な摂取源がコーヒーであることが明らかとなった。さらにクロロゲン酸は、脳、神経、肝臓、腎臓、循環器系など多岐にわたる器官に対して保護的に作用し、糖代謝の改善、脂質代謝の促進、血圧低下、抗うつ作用などの効果が期待されている。
カフェイン
カフェインは中枢神経を刺激して覚醒作用をもたらし、集中力や運動パフォーマンスの向上、脂肪燃焼や基礎代謝の促進に寄与する。また、2型糖尿病やパーキンソン病の発症リスク低下など、多面的な健康効果が報告されている。ただし、過剰摂取すると中枢神経系が過剰に刺激され、めまい、心拍数の増加、興奮、不安、震え、不眠、下痢、吐き気などの健康被害を引き起こすことがある。内閣府食品安全委員会では、健康な成人におけるカフェインの1日摂取許容量に明確な上限は定められていないが、妊婦や薬剤を服用中の人は摂取に注意することが求められている。なお、米国疾病予防管理センター(CDC)は、カフェインとアルコールを同時に摂取することで、カフェインがアルコールによる機能低下を覆い隠し、飲酒量が増える可能性があるため、健康被害のリスクが高まると指摘している。
全日本コーヒー協会HP「コーヒーと健康」について
当協会では、コーヒーと健康に関する正確な情報の提供を目的として、1996年から2021年まで「コーヒーと健康」をテーマに、全国の大学や研究機関に所属する研究者に対し、研究助成を行ってきた。これまでに約300件の研究成果が発表され、コーヒーの健康機能に関する科学的知見の普及に貢献している。現在はこれらの研究成果をアーカイブ化し、協会ホームページに整理中である。一般の方々はもちろん、コーヒー研究者にとっても参考となる情報を提供することを目的としている。今後もコーヒーの健康機能に関する科学的知見をさらに深め、消費者の健康増進とコーヒーの消費振興を目指していきたい。
株式会社SL Creations 健康サポート推進室
秋山里実
生体蛋白質のアルデヒドによるAGEs化は、単なる「タンパク質の変性」にとどまらず、組織レベルでの老化・機能低下、炎症、酸化ストレスを通じて、様々な病気(糖尿病性合併症、動脈硬化、認知症、がんなど)のリスクを高める。中でも血管、腎臓、脳神経系に与える影響は大きく、動脈硬化、心筋梗塞、脳卒中、糖尿病性腎症、腎不全、アルツハイマー型認知症などの重大リスク要因となる。また、老化肌、黄ぐすみ、しわ・たるみや、肝線維症、脂肪肝の悪化を招くなど、生体内で糖化反応(メイラード反応など)により生成される内因性AGEsの蓄積は「病的老化(pathological aging)」のリスクとなる。
慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート(KGRI)の野村周平特任教授らと、米国ワシントン大学保健指標評価研究所(IHME)による国際共同研究グループは、全国47都道府県における1990年から2021年までの健康傾向を包括的に分析した結果を発表した(https://www.keio.ac.jp/ja/press-releases/files/2025/3/21/250321-1.pdf)。2021年時点で日本の平均寿命は85.2歳となり1990年から5.8年延伸した一方で、健康寿命との差は9.9年から11.3年へ拡大、「健康でない期間」の長期化が示された。主要死因も認知症(アルツハイマー病など)が第1位となった。高血糖や過体重・肥満など生活習慣関連リスクも深刻化、慢性疾患対策の必要性を示唆している。
高齢化が進行する中、内閣府や厚生労働省の調査では「健康に気をつけている」と回答する人の割合が増加傾向にあり、健康寿命の延伸に対する関心は高まっている。一方で、運動習慣を有する者の割合は約30%前後で横ばいにとどまる。適正体重を維持できている人の割合も減少傾向、特に若年層で過体重・肥満率が増加している。食生活改善への取り組みが進むものの、実際の栄養バランスの改善には十分に結びついていないのが現状だ。
糖化ケアは①食後高血糖(=血糖スパイク)の抑制、②AGEsの生成抑制、③AGEsの分解促進の3段階に分けられる。「AG当量」は同志社大学米井研究室の研究により解明・標準化された「食品の抗糖化活性を示す指標」で、抗酸化物質の抗酸化活性のように食品含有成分の糖化を抑える働きをAGEs生成抑制作用の強さで示す。食品中の糖質の吸収度合いを示すGI値とは異なる。当社では、自社製品に「AG当量」を提示、健康意識向上と行動変容の動機づけを図っている。AGEs生成抑制作用は野菜、果物、スパイス、ハーブ類で確認され、AG当量500㎎以上/日を目標に食生活に取り入れることで健康維持に役立つと考えられている。以上を踏まえ、生活者に対し糖化ケアが健康格差の縮小、栄養バランスの改善に寄与するかについて、1週間のうち4食を「AG当量500mg以上」含む食事に置換えることによる皮膚中AGEs(最終糖化産物)値の変化を調査。その結果を報告する。
【参考資料】
1,「AGEsと老化制御―糖化ストレスとアンチエイジング医学」(米井嘉一。診断と治療社)
2,内閣府「令和5年版 高齢社会白書」
3,厚生労働省「国民健康・栄養調査(令和5年)」
4,厚生労働省「健康日本21(第二次)最終評価報告書」
5,民間調査(例:SOMPOひまわり生命「健康意識に関する調査2024」
同志社大学生命医科学部アンチエイジグリサーチセンター/糖化ストレス研究センター
米井嘉一
糖化ストレスの概念は近年変わりつつある。2025年3月13日発行「Nature」特集記事における取材では酸化ストレスと糖化ストレスとの違い、生体内における糖化反応と食品中の反応との違い、生体内におけるアルデヒド生成の原因、食品中の終末糖化産物(AGEs)の意義、胎児になぜ糖化ストレス対策(GSケア)が必要なのか)について詳細に質問を受けた。その最新情報が見開き2ページで紹介されている(https://www.nature.com/articles/d42473-024-00416-5)。酸化ストレスの原因は活性酸素/フリーラジカルの過剰、糖化ストレスの原因はアルデヒド過剰である。主な生成源は糖質由来、脂質由来、飲酒・喫煙由来、エピジェネティックス(脱メチル化)由来ホルムアルデヒドである。抗酸化酵素としてSOD、カタラーゼ、ペロキシダーゼが、アルデヒド代謝酵素としてALDH、GAPDH、グリオキサレースが備わっており、それぞれの防御機構は異なる。抗糖化酵素は肝臓、腎臓、幹細胞、前駆細胞に多い。アルデヒドのCHO基は反応性が高く、細胞内外で蛋白質・脂質・DNAと反応し、修飾する。生体蛋白質とアルデヒドの反応産物がAGEsである。このように食品中AGEs生成過程とは大きく異なる。
生体蛋白質がアルデヒドによってAGEs化することが悪いのであって、食品中AGEsは、アクリルアミドを除けば、ほとんどが有益である。コーヒー、味噌、醤油に含まれるメラノイジンの研究がもっとも進んでいる。メラノイジンの効能として、食の味と香りが豊かになること、抗酸化作用、抗糖化(AGEs生成抑制)作用、防腐作用(発酵食品製造過程で雑菌の増殖抑制)、腸内細菌叢の恒常性維持(dysbiosisの緩和)、塩分感受性高血圧の緩和が報告されている。
人類が火を使うようになったのは50万から80万年前とされており、摂取した食餌中AGEs含有量が増加した。その頃から人類の脳容積が増大し、ゴリラやチンパンジーなどの霊長類に圧倒的な差をつけて進化した。食餌中AGEs摂取が人類の脳の進化に貢献したという仮説も提唱されている。我々人類はAGEsの味と香りを安全で有益な良い食餌と認識して、本能的にAGEs求めているのではないだろうか。
AGE-RAGE系シグナルに関しても、免疫応答細胞と内皮細胞に発現するRAGEで応答に差異があること、病的状態と健常時における反応の違いを区別して考えるべきである。組織中でAGEsとRAGEと結合した免疫応答細胞は炎症性サイトカイン生成と放出を促し炎症を惹起する。しかし食品由来AGEsを経口摂取してもせいぜい血中までであり、組織内に移行することはない。血管内皮細胞のAGEs-RAGE応答はRAGE(sRAGEを含む)産生をアップレギュレーションして、VEGF産生を促進する。VEGFは健常時には血管形成と機能維持に重要な役割を果たすが、加齢黄斑変性症の病的状態では網膜毛細血管の異常増生に関与する。また、血液脳関門(BBB)の血管内皮細胞RAGEはオキシトシン輸送体として重要な役割を果たす。RAGEを介して血中のオキシトシンが脳内に移行することにより、愛情ホルモン作用が発揮される。AGEsが豊富なおいしいものを食することによって、RAGEを増やし、愛情を発露させて、本人だけでなく周囲の人を幸せにする効能があるのではないだろうか。食品中AGEsはそのような期待がかかるのである。
【参考資料】米井嘉一。糖と脂で体は壊れる。池田書店、2025.